『ポツンと一軒家』を観ていると、都会の喧騒を忘れて、自分だけの静かな時間を過ごしたい…そんな風に感じませんか?画面の向こうに映る暮らしは、私たち誰もが心に秘めている**「理想の生き方」**なのかもしれませんません。
でも、もし本当にそんな場所に住むとしたら…?
憧れと不安が入り混じるなかで、思いを巡らせるだけで行動には移せない。
それでも、「条件や環境が整えば…」と、ついあれこれ考えてしまう。
今回はこの番組をきっかけに、「もし自分が住むなら?」という視点で、
実際に暮らすために必要なことや心構え、メリット・デメリットについて考えてみたい。

🏡 番組の魅力とコンセプト
「衛星写真から始まる人間探訪」
『ポツンと一軒家』という番組は、他の旅番組とは少し違う。
まず、スタートが“衛星写真”というのがユニークだ。
山奥にぽつんと映る建物を見つけて、「ここに人が住んでいるのか?」と調査が始まる。
地図にも載っていないような場所に、誰かが暮らしている。
その事実だけで、もう物語が始まっているような気がする。
調査スタッフが道なき道を進み、ようやくたどり着いた先には、
静かに、しかし力強く生きる人たちの姿がある。
自然と向き合いながら、自分のペースで暮らす人々。
その生活には、便利さとは違う“豊かさ”がある。
「なぜ多くの人が惹かれるのか」
この番組が多くの人の心をつかむのは、
単に“珍しい場所”を紹介しているからではないと思う。
むしろ、そこに暮らす人の“生き方”が映し出されるからだ。
都会の喧騒から離れ、自然の中で暮らすという選択。
それは、誰もが一度は夢見るけれど、なかなか踏み出せないもの。
だからこそ、画面の向こうに映る人々の姿に、
「こんな暮らしもあるんだ」と、心が動かされる。
彼らの言葉は、どれも飾り気がなく、まっすぐだ。
「ここが好きだから」「自分の手で暮らしを作りたいから」
そんな理由で山奥に住む人たちの姿は、
どこか懐かしく、そして新しく感じられる。
🏡 「仁淀川、飯南町、久万高原…番組で特に印象的だった3つのエピソード」
「ポツンと一軒家」という番組には、全国各地の“人里離れた暮らし”が登場する。
その中でも、私の住む四国や、隣接する中国地方のエピソードには、地元四国や中国地方のエピソードには、どこか親しみを覚えます。たとえば、木漏れ日が差し込む早朝の山道、薪が燃える匂い、そして地元の方言が持つ温かい響き…。画面の向こうから、その土地の空気が伝わってくるようです。
今回は、そんな地域から印象的だった3つの場所を紹介したい。
① 高知県・仁淀川町の山奥に暮らす男性
仁淀ブルーと呼ばれる清流のそば、山深い場所にひとり暮らす男性。
仁淀ブルーで知られる高知県の清流のそば。そこに、山に生きることを決めた一人の男性の物語がありました。元林業従事者である彼は、山の恵みをいただきながら、自分の手で暮らしを築き上げています。**『山は裏切らん』**と語るその眼差しには、自然と共に生きる深い覚悟と誇りがにじんでいました。
家は手作りの木造小屋で、薪ストーブと囲炉裏がある素朴な空間。
「山は裏切らん」と語るその姿に、自然と共に生きる覚悟と誇りがにじむ。
地元の人との交流もあり、孤独ではなく“静かなつながり”を感じさせる暮らしだった。
② 島根県・飯南町の山中に暮らすご夫婦
標高600mを超える山中にある古民家で、農業と木工を営むご夫婦。
ご主人は木工職人として家具や器を制作し、奥様は畑で野菜を育てながら、季節の保存食を丁寧に作っている。
家の周囲には棚田が広がり、春には山菜、秋には稲穂が風に揺れる。
「ここに来てから、時間の流れが変わった」と語る奥様の言葉が印象的だった。
都会から移住して20年、地域行事にも積極的に参加し、地元の人々とも深い絆を築いている。
③ 愛媛県・久万高原町の山間に暮らすアメリカ人夫婦
茅葺き屋根の道場を自ら建て、古武術「自然道」を教えるアメリカ人夫婦。
古代米の田植えや、山菜を使った料理など、自然と調和した暮らしを実践している。
道場は木と土と藁で作られ、まるで昔話の世界のような佇まい。
「自然の中で心を整える場所を作りたかった」と語るご主人の姿に、哲学的な深みを感じた。
地域の人々とも交流があり、文化の違いを越えて“共に生きる”姿勢が伝わってきた。
それぞれの場所に、それぞれの物語がある。
便利さとは違う“豊かさ”を求めて暮らす人々の姿は、
どこか懐かしく、そして新しい。
私たちの身近にも、こんな暮らしができる場所があるのかもしれない──
そんなことを考えながら、次の放送を楽しみにしている。
🧑🌾 ポツンと一軒家に暮らす人の傾向性
番組を見ていて感じるのは、そこに住む人たちには、ある共通した“気質”があるということ。
もちろん、年齢も背景もさまざまだけれど、どこかに「自分の暮らしを自分で作りたい」という芯の強さがある。
🌿 自然志向
山の水を引き、薪で火を起こし、畑で野菜を育てる。
便利さよりも、自然と共にあることを大切にする人が多い。
「自然は厳しいけど、裏切らない」と語る人の言葉には、深い信頼が感じられる。
🪵 職人肌
木工、陶芸、農業、養蜂──。
手仕事を大切にし、自分の技術で暮らしを支える人も多い。
道具の使い方や、家の造り方にこだわりがあり、暮らしそのものが“作品”のように見えることもある。
🫱 地域との共生
「ひとりで暮らしているようで、実はそうじゃない」
地域の人との交流を大切にし、行事に参加したり、野菜を分け合ったり。
孤独ではなく “静かなつながり” を持っている人が多いのも印象的だ。
👥 年齢層と移住のきっかけ
年齢層は幅広く、60代以上の方が多い印象だが、最近は30〜40代の移住者も増えている。
きっかけは「都会の暮らしに疲れた」「自然の中で子育てしたい」「自分の時間を取り戻したい」など。
それぞれの人生の転機に、“ポツン”という選択肢が浮かび上がってくるのかもしれない。
🏡 もし自分が住むなら?──現実的なステップ
番組を見て「こんな暮らし、憧れるな」と思った人は多いはず。
でも、実際に住むとなると、何から始めればいいのか分からない。
ここでは、現実的なステップをいくつか紹介してみたい。
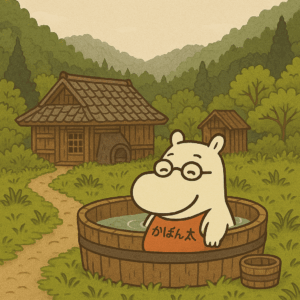
🏠 空き家バンクを活用する
各自治体が運営する「空き家バンク」では、地域の空き家情報を公開している。
香川県でも市町ごとに空き家バンクがあり、条件付きで格安物件が見つかることも。
まずは地元の役場や公式サイトをチェックしてみるのがおすすめ。
🤝 地域支援制度を調べる
移住者向けの支援制度も充実してきている。
家賃補助、改修費の助成、農業体験プログラムなど、自治体によって内容はさまざま。
「地域おこし協力隊」などの制度も、移住の第一歩として注目されている。
🧳 短期滞在や体験移住から始める
いきなり移住するのはハードルが高い。
まずは「お試し移住」や「体験宿泊」などを利用して、地域の空気を感じてみるのがいい。
地元の人と話すことで、暮らしのリアルが見えてくる。
香川県でも「お試し住宅」や「移住体験ツアー」を実施している市町があるので、気軽に参加してみるのも一つの方法。
⚖️ ポツンと一軒家のメリット・デメリット
「こんな場所に住んでみたい」と思ったとき、まず気になるのが“実際どうなのか”ということ。
番組を通して見えてくる、ポツンと暮らすことのメリットとデメリットを整理してみたい。
✅ メリット
• 自然との共生:四季の移ろいを肌で感じながら暮らせる。空気も水も澄んでいて、心が整う。
• 静かな環境:騒音や人混みとは無縁。自分のペースで生活できる。
• 自分らしい暮らし:家の造り、畑のレイアウト、仕事のスタイル──すべてを自分で決められる。
• 創作や仕事に集中できる:陶芸、木工、執筆など、静かな環境が創造性を高めてくれる。
❗ デメリット
• インフラの不安定さ:水道・電気・通信が整っていない場合も。冬場の雪や台風の影響も大きい。
• アクセスの悪さ:買い物や病院は車で片道30分。急な体調不良の時、どうする? 冬の雪道は運転できるか?想像するだけで、現実に引き戻される感覚です。
• 孤独感:人との距離がある分、寂しさを感じることもある。
• 害獣・虫・自然の厳しさ:イノシシ、ムカデ、雪かきなど、自然との“闘い”もある。
🧰 準備するもの・心構え
実際に“ポツン”な暮らしを始めるには、物理的な準備と、心の準備が必要になる。
🧭 生活インフラの確認
• 水源(井戸・沢水)、電気(太陽光・発電機)、通信(Wi-Fi・携帯電波)
• トイレや風呂の設備も重要。古民家の場合は改修が必要なことも。
🚗 移動手段
• 車は必須。四駆や軽トラがあると便利。
• 雪道や山道に対応できる運転技術も求められる。
🧑🌾 暮らしの道具
• 農具、薪割り道具、防獣ネットなど
• DIYスキルがあると、家の修繕や設備づくりに役立つ
🫱 地域との関係づくり
• 挨拶、行事への参加、地元の人との会話
• 「ひとりで暮らす」ではなく「地域の一員になる」意識が大切
🗺️ 候補地はある?──香川や近隣の“気になる場所”
香川県にも、ポツンとした場所は意外と多い。
山間部や島しょ部、廃校跡や空き家など、少し目を凝らせば“気になる場所”が見えてくる。
🌄 香川の候補地
• 塩江町の山間部:温泉地として知られつつも、奥には静かな集落が点在
• 小豆島の中山地区:棚田と古民家が残る地域。移住者も増えている
• 三豊市の仁尾町・高瀬町:海と山に囲まれたエリア。空き家バンクも活発
🔍 探し方のヒント
• 地元の空き家バンクや移住支援窓口をチェック
• Googleマップで“道が細くなる場所”を探してみるのも面白い
• 実際に足を運んでみると、写真では分からない空気感がある
結び──一歩踏み出すために
「ポツンと一軒家」という番組は、
不便さの中にある豊かさ、孤独の中にあるつながりを教えてくれる。
もし自分が住むなら──そんな問いを胸に、静かに思いを巡らせる。
そしていつか、条件と環境が整ったとき、
自分だけの“ポツン”を見つける日が来るかもしれない。
ポツンと一軒家に住むことは、ただ場所を変えるだけでなく、暮らし方や生き方そのものを見つめ直すことかもしれません。
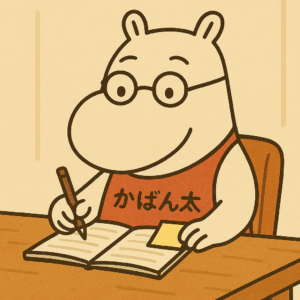
■イラストについて
「かばん太」イラストは、著作権者である当ブログ運営者がオリジナルで制作した作品です(一部デジタルツールを活用して制作)。 無断転載・使用・二次加工・商用利用を禁止しております。 ご利用をご希望の場合は、事前にお問い合わせください。 ©kabanta(かばん太)Illustration

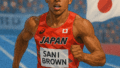
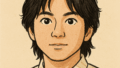
コメント